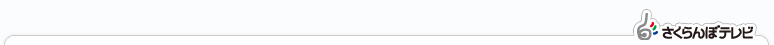
第2回「さくらんぼ文学新人賞」一次選考通過作品

第2回さくらんぼ文学新人賞
応募総数554作品
一次選考を通過した作品は以下の23本です。
なお、二次選考の結果は9月中旬頃に発表いたします。
※作品順不同
※コメント最後の( )内署名についてはページ下の「一次選考であがった声」を参照。
タイトル | 著者名 | コメント |
| パラダイスに降る雨 | 村山小弓 | 老人介護の世界に生きる人物たちが魅力的に描かれていて、ラストまで一気に読ませる。(深) |
明日の奇跡 | 葉丸みか (山形県) | 絶望のなかでのたうちまわる人物たちの感情や行動がディティール豊かに描かれていて迫力がある。(深) |
| 動けば正義 | まるこばるど (埼玉県) | PTA役員選出会議という短い時間の中で、人々のキャラクターが見事に立ち上がっている。(東) |
| 楽園への鍵 | 濱口香代子 (大阪府) | 短篇に必要な大きな場面転換がとても効果的。日常の小さな謎も効いている。(東) |
| ホーム レス ホーム | 天野月詠 (福岡県) | それぞれの人物が魅力的。さわやかな読み心地で、あと口のいい小説。(東) |
| カラー・ウォーター | 倉津典花 (東京都) | 三姉妹のそれぞれの「今」を切り取ったオムニバス小説。今回もっとも書ける人だと思った方の作品です。第一話の末妹(この子が実にチャーミング!)が思っているほど、お気楽な開放人生を送っているわけではない長姉の姿(第三話)まで、ものすごく手触りのある(&考え抜かれた)エピソードの集積で読ませます。どの姉妹も忘れがたい。猛烈に続きが読みたくなります。逆転の皮肉ですが、賞獲りレースでは、この“後引き”がネックになるかもしれません。(温) |
| ピース[piece] | 山口奇蘭 (中華人民共和国) | 失恋の淋しさを、体の温もりで埋めようとした30代女性の話。恋愛がうまくいっているときは恋愛と性愛に区別はないけれど、恋愛を失ったとき、性愛が一人歩きし始める。性の垣根が高かった頃、欲望はもっとヒリヒリしたものだった気がしますが、ネットで男女がお手軽に性を楽しめる現代は、“これ、いらない”と捨て去る方がチリチリと身を焼く。その辺を気取らない言葉で等身大に書いたところに、同じ女性としてのリアリティを感じました。(温) |
| 父はDEATH郎 | 土田ふじみ | 四郎さんとか志郎さんとか、そういう名前の父親なのかなと思ったら、なんと「死ね」という怒りの命名。直球に笑いました。その「デス郎さん」に家族中が振り回されてきたエピソードを、中年になった女主人公が年代記風に回想。その合間に、実家に向かう「今」が挿入されます。なぜこの「今」の描写が必要なのか? それが明らかになるオチが秀逸。本当にビックリしました。このオチで、家族小説におさまらない柄の大きさを獲得したと思います。“怒りのユーモア小説”で押し切った手腕を、おおいに楽しみました。(温) |
| 南国飄飄 | 古内一絵 (東京都) | 日本列島の最南端、波照間の海岸に激戦地ボルネオを幻視する戦争の生き残り老人にシビれました。遠い記憶の中に、まだらのように浮かぶ原色の風景。その回路を描いて痛切。戦争が青春、そんな世代が退場しつつあることを思い知らされます。老人、40代キャリア女性、民宿の青年と、三世代を意識されたと思いますが、この作品の情感には、青年のオチはいらず、老人とキャリア女性で十分だった気がしないでもありません。タイトルについてですが、これ「飄飄」ですか……? 「渺渺」だと感じた私は、誤読していますか?(温) |
| 適齢期を過ぎてしまったら | 高橋由佳 | 文章のリズムがいい。ストーリー的には新鮮味はないし、筋の運びにも強引さはあるものの、「伸びしろ」を感じさせる魅力はある。(吉) |
| 赤い実ひとつ | 小林旬子 | 文章のリーダビリティと、設定のオリジナリティが、頭半分ほど抜けていた。ただ、物語全体としての線は弱い。(吉) |
| 戻れないせなか | 入江沙希 | クラスメートと積極的に交わろうとしない高校生の少女。ひょんなことから隣りの席の男子生徒と話すようになる。彼はサッカー部に所属するスポーツマンだったが、男にはもったいないほどきれいな肌と顔立ちをしていた。自分が化粧することより、他人にメイクるすことに興味を持っていた少女は、自宅で彼を相手にメイクの実践を行う。その行為を通して、彼女は自分の取るべき道をみつけていく。一方男子生徒はメイクされて変身をとげていく行為に快感を覚えていく。 |
| 叙情的な癒し | 二本松泰子 (東京都) | 売れっ子落語家の事務所に出入りする女性。ファンが高じて、事務所の電話番などをときおり任せられている。落語家に対するほのかな想いと、亡くなった母親に対する疎ましい記憶が渾然と描かれていく。突然、彼女のアパートに旧友が転がり込み、物語が動いていく。 |
| 群青の海にリリース | さくま夜空 (愛知県) | 14歳の少女が垣間見た大人の世界。本当の自由を得るには悲しみがあっても自立しなくてはと知っていく過程を、魚をモチーフに率直に描いている。ガラス作家の母、貿易商の父、美大に通う兄がいる家庭は「普通」と解離していても、物語としてまとまりがありました。(青) |
| 熊猫(ぱんだ)の囁き | 邢彦 (大阪府) | 日本に帰化した中国人女性の生活が、夫の裏切りで一変する。失意からはい上がる道を探る主人公の心理を描こうとし、作者が中国出身であるため、自然、世界を広く見渡した物語になっている。お好み焼き店で頑張る日本人女性、しのぶのキャラクターが闊達で胸打たれる。夫の愛人に対する主人公の心の持ちようも良いのですが、物語の構え、筆致がまだ自家薬籠中のものとなっていない印象を受けました。(青) |
| 映画女優 | 原村美杉 (東京都) | ひとりの女性の人生がよく描かれている。登場人物の行動と心理に無理がない。読者を意識して書いていることにも好感が持てた。(柚) |
| 少女とナイフ | 武原一仔 (北海道) | 主人公の少女が生き生きと描かれ、無理なくストーリーが流れていく。読者をひっぱっていくための謎もあり、面白く読めた。(柚) |
| フーカの家 | 遊座理恵 | 軽妙な語り口が板についていますね。それに流されない物語の力もあると思いました。最初、主人公の男女はややつかみどころなく映りますが、次第に読者に印象づけていく描き方も、見事。飄々とした展開の中に、やがて訪れる切なさが心に残ります。(三) |
| 暗黒の幸運 | 奈月俐都 | ユーモアが効いているし、やがて滲み出てくるブラックな味わいもいい。この賞の応募作には珍しい本作の個性は、ミステリ、あるいは幻想と怪奇の分野に属するものでしょう。最後は予定調和の域を出ないうらみもありますが、この応募者には、短篇作家の才気を感じました。(三) |
| 愛の行為 | 斎藤きあ (愛知県) | あっけらかんとしていたり、ぶっきらぼうだったり。とにかく、言葉の使い方にプリミティブな魅力を感じました。主人公カップルの描き方に、切実なものがある。愛を正面から語りながら、ありがちな甘さに流されない強さがいいですね。(三) |
| 俯瞰 | 羽鳥ひより (東京都) | 夫がまきこまれる事件がたんたんと、しかし充分密度のある語りで読ませるし、屈折した夫婦関係、男女関係をクールに捉えているのもいい。着地がやや弱いが。 (池) |
| 吾輩は猫を産んだ | 三咲ヒナ (愛知県) | ある家族の歴史のアクセントがすべて猫たち。その猫たちの位置が正確にはかられているし、猫の個性も生き生きと捉えられてあって楽しい。 (池) |
| 骨 | 池子とら (山形県) | 物語が停滞しているのが難であるが、ひとつひとつの挿話がもつ重さとイメージの確かさで、独自の世界が醸しだされている。 (池) |
【 一 次 選 考 で あ が っ た 声 】
一次選考にかかわった方々よりコメントをいただきました。
◆前回はファンタジーあり、日常の一場面を物語にしたものありで、多様な小説が読めたのですが、今年は小説として形になっていないものが目立ちました。個人的なイベントをそのまま書いたら打ち明け話、憂さはらしで、普遍的な物語ではない。枚数に達したから応募するのではなくて、そこに読者に伝わり、共感される物語があるか、自分が小説にしようと思ったことを、自分ができる最善の形で書けているか、をもう少し眺めてほしい。一考してみるだけで、自分の文章が織りなす形はまた変わってくると思います。(青木千恵氏)
◆抜きん出た小説もなかったがひどい作品もないというどんぐりの背比べ。小説内小説や他小説からの引用、短歌、俳句は本人の思い入れほど効果はなく、むしろうるさい。原稿の書き方の最低限のルールは守るべし。読みにくい書式設定は作品の質に関わらずマイナスイメージになる。とにかく完成した小説は最低3人の人に読んでもらって感想を聞くこと。折角100枚近い物語を作ったのだから。(東えりか氏)
◆「自分語り」が露骨な作品は減ったような気がします。しかし一所懸命物語を作ったようでも、すぐ背後から「作者自身」の姿すぐ透けて見えてしまうような作品があい変わらず目立ちます。「自分語り」作品とともに、そういった作品は得てして独りよがりで、読んでもらう者の存在をどこかに置き忘れてしまっています。
また、昨年と同じ物言いになってしまいますが、短編は長編のシノプシス(梗概)ではありません。枚数は短いのに、だらだらと書き流している印象を受ける作品が多すぎます。選考委員はじめとした作家の、優れた短編作品を読むことも肝要かと思います。読めば書けるということではないけれど、書くことの滋養に繋がることは間違いないでしょう。(西上心太氏)
◆今回は思わず「おお」と乗り出す力作が多く、このさくらんぼ文学新人賞が二回目にして、すでに質を確保したことを確信しました。応募される方々の年齢も幅広く、その意味でも、読むことで「広い世界」を旅したので、ここでは選外作品について触れたいと思います。
今回はユーモア作にいいものがありました。「絶滅変種保育ダイアリー」は、規格外である我が息子にやきもきしっぱなしの母の人生を、突き抜けた明るさで描いています。最後のやけっぱちみたいな一行も、実に爽快。女の“笑い飛ばし型”の小説は、おもに負け犬ゾーンの専売特許でしたが、母世代に出てきたことは画期的だと思いました。いまでも選外にしてしまった自分が憎いです。
東洋医学に凝る健康志向の妻に比して、夫がどんどん弱っていくブラックな味の「好歓」も捨てがたい作品。こういった言外を読ませる作は、人物造形が命。この作品は夫の俗っぽさがとてもよく描けていました。選外にしてしまった自分をいまでも疑っています。
「ロスト・ジェネレーション」は、就職超氷河期にぶち当たってしまった世代の女性からの、いわば“現場報告”。内容の痛切さに、“し~ん”。「幽霊旅館」は、愛する死者と言葉を交わす、誰もが夢見るファンタジーですが、意表を突くオチに“こういう手もあったか”と感心。「輪郭の消えた男」も、なんともいえない哀切さがありました。どれも、いまでも心残りです。(温水ゆかり氏)
◆わたしが読ませていただいた50作に限っていえば、昨年よりも全体的にレベルが上がっていると感じました。とりわけ文章に関しては、ほとんどの作品が他人に読ませる力を備えていて、頼もしい。その反面、小さくまとまってしまっている作品も多く、技術は劣っても、意気盛んな作品がもっとあってもいい、とも思います。また、80枚という限られた枠の中で、何を書き、何を省略するかの判断が大事でしょう。読み終え、「そこから先が読みたいのに」と残念な思いに捉われた作品が、今年も目につきました。(三橋曉氏)
◆A評価をつけた2作は、B評価の作品と比べてずば抜けた出来、というわけではなく、どちらも「頭半分」くらい、な感じです。今年は「そこそこ疵なく書かれた作品」が多かったですが、そのどれもが「物語が閉じていない」ものでした。また、「読み手を意識していない作品」、要するに「書き手が自分のために書いた作品」でした。(吉田伸子氏)
◆「絶対に賞をつかむ」という野心を感じさせる作品が少なかった。難病や出産や不倫といったテーマを工夫せずに扱った類型的な物語が目立った。自分のために書いたような読み手を意識しないエゴイスティックな作品が多かったが、総じて文章のリズムはよく、書き続ければきっと伸びるであろう個性を保有した書き手が多数いたのが収穫だった。(深町秋生氏)
◆読者に向けて書かれたものではなく、自分に向けて書かれた作品が多かった。自分が書きたいこと(テーマ)を描くのは大切なことだが、それをいかに読者にわかりやすく伝え、飽きさせないで最後まで連れていくかという仕掛けが不足しているように思う。今回、うえにあげた作品はそこが巧みに描かれていた。(柚月裕子氏)
◆半径数メートルの話が多すぎる。恋愛、家庭不和、病、派遣切り、旧友との再会、不倫と題材が平凡。題材が平凡でもプロ作家が書くと面白いのは、キャラクター、ストーリーテリング、プロットが平凡ではないから。独自の切り口(個性)があるから。読者を愉しませよう、驚かせようという考えがあるから。もっと読者を意識して愉しませてください。自分の個性が何かを考えてください。 (池上冬樹氏)