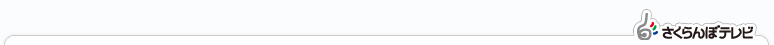
スペシャルインタビュー
さくらんぼ文学新人賞第2回大賞受賞者・邢彦氏インタビュー
インタビュアー/文芸評論家 池上冬樹氏
■作家になろうと思ったきっかけ
―― 大賞受賞おめでとうございます。一報を聞いてどんな気持ちでしたか?
邢彦 とても嬉しかったです。
―― 中国にいた頃から、作家になろうと思っていたんですか?
邢彦 わたしの母方の祖母は読書が好きで、家にたくさんの本がありました。だから、小さい頃から本を読んでいました。でも、中国にいた頃は若すぎたせいか、まだ書こうという気持ちはわいてこなかった。書きたいと思ったのは日本に来てからで、日本に来て言いたいこと、伝えたいことがあると気づき、日本語という道具を使って小説という形で、自分の考えていることを表現できれば、と思うようになりました。
―― 中国語で書いて日本語に訳すという方法もありますが、日本語で小説を書こうと思った理由はなんですか。
邢彦 これは本当に不思議なことですが、なぜか日本語だったら、自分の思いを表現しやすいような気がしたんです。中国語には漢字しかないけれど、日本語には平仮名があります。漢字と平仮名がまじることで流れるような文章になるような気がします。
それに、来日してから翻訳事務所をかまえて翻訳の仕事をしてきたのですが、会社のカタログや会議用資料を翻訳する仕事が多かったんです。そのようなものは、使った後はゴミ箱行きですよね。そう考えると、翻訳者の性とでもいうのでしょうか(笑)、自分のものを残したいという気持ちにだんだんなってきました。
■エンターテインメントか純文学か
―― 応募原稿の投稿歴を読むと、昨年から、いろいろな文学賞に応募されていますね。
邢彦 去年の四月から小説を書きはじめて、書いた作品は全部応募しました。
―― いままで応募した作品は、どういったものが多かったんですか?
邢彦 わたしはもともと中国人でしたので、中国人が日本に来て、そこで出会った人々との間で起こった出来事などを書いてきました。
―― 日本には私小説というジャンルがありますが、そういうジャンルを書いてきた、ということでしょうか。
邢彦 私小説ではないですね。自分の私生活や身の回りのことをそのまま書くということではなく、あくまで自分の感じたものを、フィクションで作りあげていくというものです。
―― エンターテインメントと純文学というジャンルがありますが、どちらが好きですか?
邢彦 むずかしい質問ですね。たぶん、傾向でいうと純文のほうだと思います。でも、純文学であっても、やはり作者自身の思いをより多くの読者に理解してもらえたほうがいいと思いますので、面白く読んでもらえるように、構成や登場人物を考えたりしています。出来ればエンターテインメントの要素も取り入れて、なおかつ深みのある作品を書こうと思っています。
―― いまはあまり使わない言葉ですが、エンターテインメントと純文学の中間のようなジャンルで「中間小説」というものがあるんですが、そういった作風かな、と思ったんですよね。中国と日本の文化の衝突とか、日本で生きていくうえでの悩みなど、ネタはたくさんあると思いますね。
■影響を受けた作家
―― 日本語で小説を書こうとしたとき、きっと日本文学も読んだと思うのですが、なにか影響を受けた作品はありますか。
邢彦 とにかく広く浅く読み漁っていたんですが、そのなかで開高健は何度も読み返しました。たとえば、「パニック」と「玉、砕ける」。とくに「玉、砕ける」を読んだときは、最初はなにを書いているのかわからなかったんですが、最後の、中国人作家、老舎の死に触れた部分を読んだとき、ああそうなんだ、と作者の意図に気づき、じわっときました。
―― 開高健はひとつひとつの単語を大切にする作家ですから、噛み砕いた感じの文体になっていますよね。
邢彦 そうですね。ほかには、井上靖なども読みました。先日、図書館に行って偶然「壷」という作品を見つけ、コピーして持ち帰ったんです。これも老舎の死を題材にしている作品なんです。とても短い作品なんですが、自宅で読んで号泣しました。あと、井伏鱒二とか、山崎豊子の作品も読みました。
―― 小説以外では、詩やエッセイはどうでしょう。詩のほうに行こうという気持ちは、なかったんですか?
邢彦 エッセイなどを書いてみたことはありますが、詩というものはもっとハードルが高いような気がします。さらなる洗練さが求められるような気がします。
■省略する美学
―― 今回の選評でも書かれていますが、邢彦さんが書くヒロインは、泣き叫んだりわめいたりしませんよね。それは自分の個性でしょうか。
邢彦 そうですね(笑)。沈黙は金なり、という感じでしょうか。言わないところが美しいと思っている部分はありますね。とくに小説を書きはじめて、言葉というものはもっと惜しんで書かなければならない、書かないで感じてもらうというのが一番大事ではないかな、と思うようになりました。
―― 省略する美学とでもいうのでしょうか。行間に思いをこめるという抑制のきいた美しさがあります。邢彦さんの作品には、折り目正しい昭和の文学を思い出させるものがあります。いい文体だなあと思いましたね。
邢彦 自分の文体というものがまだまだ模索中なので、翻訳作品にならないように、出来るだけ日本の読者にとって違和感のない日本語に仕上げようという気持ちはすごく大きかったですね。
―― 今回の作品は五作目と聞きましたが、今回の作品がいままでで一番上手く書けた作品ですか?
邢彦 そうですね。史上最高の作品です(笑)。
―― 僕は運営委員として一次選考から関わっていますが、二次にあがってきた邢彦さんの作品を読んだとき、「これで決まりだな」と思いましたね。それは僕だけではなくて、邢彦さんの作品を読んだ誰もが、すんなり上にあげてきました。その評価のひとつが、スムーズな日本語だったんですが、これだけ日本語をマスターするのは大変だったんじゃないですか。
邢彦 がんばりました(笑)。というか、がんばってます。まだまだ、足りないです。
■次回作/書いていきたいもの
―― 次回作は考えていますか?
邢彦 去年、北日本文学賞に応募した三十枚のものがあるんですね。小説を書きはじめた頃の作品で、思い入れがある作品なんです。それを伸ばして書いている最中です。
―― 長編を書こうという気持ちはないですか?
邢彦 長編まではいきませんが、昨年の北九州市自分史文学賞に二百三十四枚の作品を応募しました。長いものなので、書く前は不安があったんですが、いざ書いてみて、出だしの部分がうまく書けた後は、スムーズに最後まで一気に書くことができました。
―― 今回の作品も、選考委員の北上次郎さんが、冒頭の部分がすばらしくいい、と言っていました。淀屋橋の欄干の暖かさや景観が、俯瞰して見える感じでしたね。作者の頭のなかに、風景ができあがっているんでしょうね。
邢彦 書きはじめは、いままで自分が見てきた風景をイメージして書いていったんですが、大事なシーン、今回の作品でいうならば、最後の、主人公が自転車に乗って淀屋橋を通過するシーンは、もう少しなにかが足りないという気持ちになって、実際に自転車に乗って行きました。そして、橋の上に立って感じたもの、普段、見慣れている風景というものには、いろんな宝物が隠されているんだな、という思いになりました。
―― これからますますいろいろな作品を書いていくと思うのですが、一番書きたいものはなんですか?
邢彦 人生というのは有限なものなので、書ける作品は限られていると思うんですね。だから一作一作、できるだけいいものを書いていこうと思っています。私は中国生まれで、中国人の血が流れている。だけど、縁があって日本に来た。だから、中国人の情の部分と日本人の情の部分、中国人と日本人のふれあいを書いていこうと思います。
―― いい作品をたくさん書いてください。期待しています。
(09年11月 さくらんぼテレビにて)